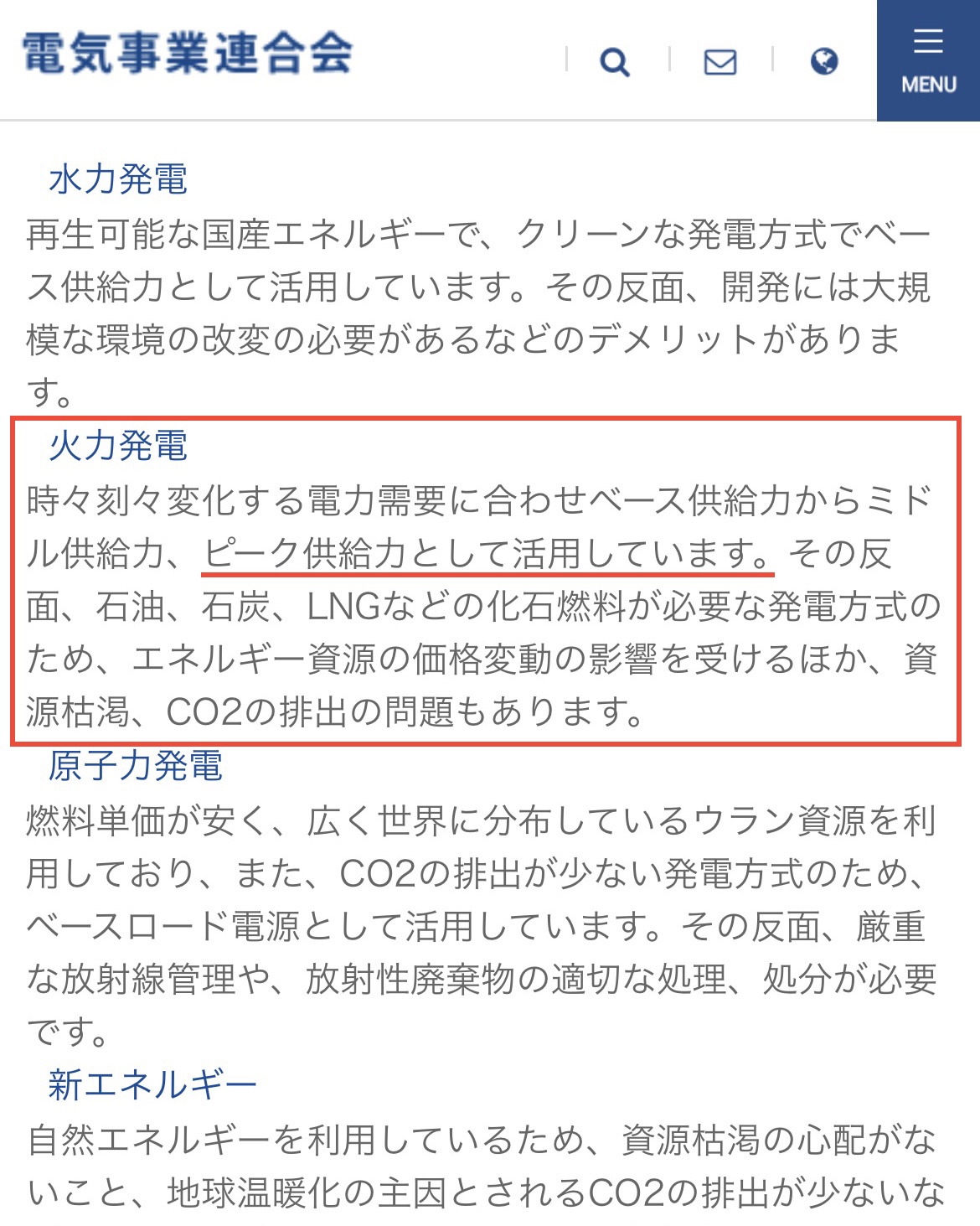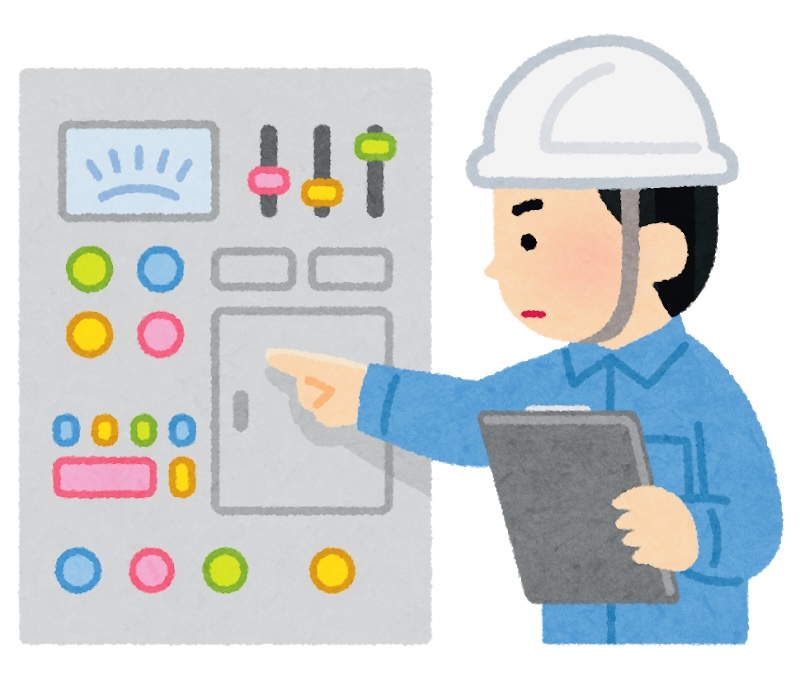【電力ピークカット】 みんなが協力して達成できる、大規模な省エネと、火力発電の抑制
お仕事で、「電力ピークカット」というキーワードを聞かれた方がある程度おられるかも知れませんので、意味と仕組みと、生活の中で取り組める内容を紹介します。
電力契約はお互いに上限値で合意で、超えた場合はペナルティが発生
電力は主に産業用と家庭用に分かれており、産業用の工場や病院などの施設には、電力会社との個別契約で、いかなる時も取り決めた電流値を超えてはなりません。
もし、超えた場合は契約電流値の上昇に応じた料金体系に値上げされ、その料金体系は電流値の上限変動に応じて1年間継続する契約条件になっています。
すなわち、電力会社は、供給している産業用の施設などごとに、使用する最大の電流値を取り決めており、それに応じた発電計画を立てて、品質のよい電力供給に努めていることになります。
両者で取り決めた計画を超えた場合は、電力会社が他の供給先へ電力を安定供給するために、緊急的な発電を実施しなければなりません。
電力会社の計画のピークを超えた緊急的な給電策は火力発電
この緊急的な発電に主に使用される手段は、必要に応じて細かな運転調整可能な火力発電所であり、温室効果ガスの増大や、限りある化石エネルギーの使用で、環境に多大な影響を与えることになります。
上限値を超える主な要因
産業用の施設が契約電流値を超える場合として、夏や冬の空調設備の動力機器などが消費する電力が主な要因です。設備の担当者は常に電力メーターをモニターしているので、ピーク値を超えないように、電力ピークカット対策を実施します。
具体的な手段としては、空調機器の運転方法を自動運転から手動運転に切り替えて、上限値を超えないように消費電力を抑える対策を実施します。
一般に、この契約に対する一連の消費電力のカット(消費抑制)作業を「電力ピークカット」と定義しています。
電流値が超えてしまうと、経済的なペナルティが発生するだけでなく、電力会社の配電や電力バランスに影響して、さらに緊急稼働させる火力発電所での環境負荷まで発生させることになるので、個別の施設の問題だけではないのです。
生活の中で出来ること
私たちの生活の中で、電力ピークカットに協力出来ることもあります。
あらかじめ気候や最高気温や最低気温、大手電力会社の供給計画を把握しておき、ピークが予想される時間帯に備えて、家電製品だけに頼らず服装や換気設備などの点検など、あらかじめ計画しておくことで、電力消費のピーク時に、消費電力を抑えることができます。
この取り組みは、電力ピークカットという、大きな取り組みに協力するだけではなく、省エネに取り組むことで、おサイフにもやさしくなることが、ご理解いただけると思います。
まとめ
SDGsの持続可能な開発目標として、一人ひとりが「持続可能な社会の構成員」であることを自覚して、生活の中で積極的に省エネに貢献するために、知らない知識を調べ理解して、今の時代の生活に必要な知識をしっかりと把握して、将来の世代に良い状態の環境を引き継げるように努めなければなりません。
参考リンク
- 電気事業連合会:
https://www.fepc.or.jp/
- 資源エネルギー庁:
https://www.enecho.meti.go.jp
- 国連広報センター 2030アジェンダ:
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
- 作成:令和2年11月3日
- 文:能登 健
- 出典元:電気事業連合会、資源エネルギー庁、国連広報センター
- 絵:いらすとや