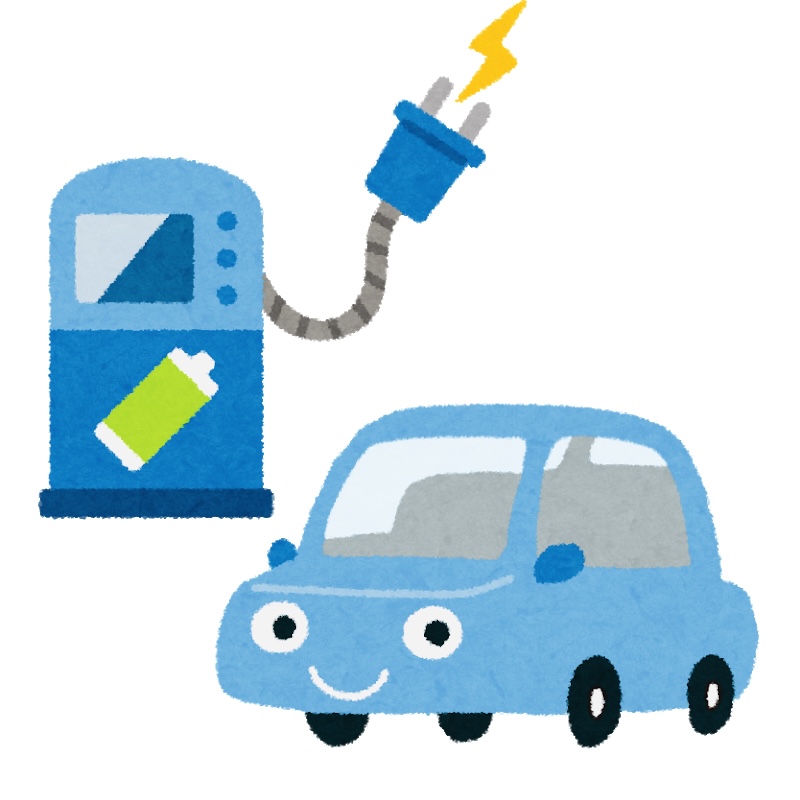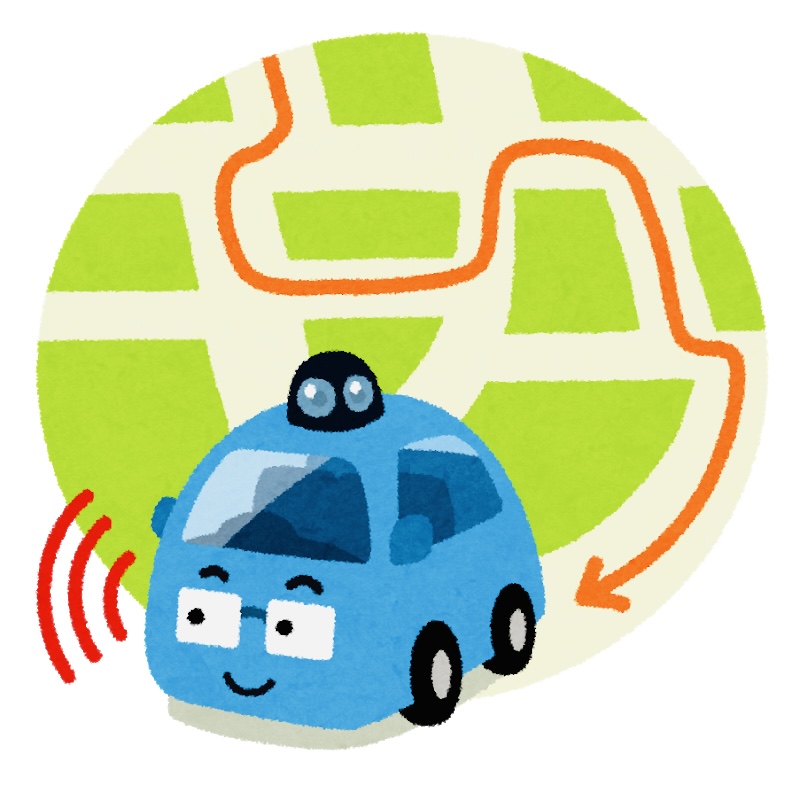【自動車社会の変化】 自動車やマイカー(自家用車)の買替えタイミングは、いつがいいの?
マイカーを買い替えようと思ってるんだけど、エネルギー問題や自動運転化がいつ落ち着くのかわからないから、買替えを先延ばしばかりして…
どうしたらいいんだろう。


そうですね。
自動車のモノづくりや利用に、環境や社会など様々なことに配慮が必要になっていますね。
日本国内でも2030年代中に、ガソリンやディーゼル軽油の内燃機関でのみ走行する自動車は、新車登録が出来なくなりますね。
今後発売される自動車の技術進歩が気になって、買替えタイミングが悩ましくなりますね。
自動運転化で長距離運転の疲労軽減や、安全性向上はとても気になるところだよね。


そうですね。
数年前からの運転支援の機能向上はめざましいものがありますよね。
さらに進化するのに期待してしまって、次の新車種を待ってしまう事が続いている人が多いですね。
燃費や環境性能に対する減税評価が厳しくなるので、本当に難しいですね!
ノッティーさんは、何か良い解決策を知ってるんじゃないの?


つよしさん、私しか知らないことなんてありませんよ。
現状でわかっていることなら、説明できますよ。
そして、つよしさんのライフステージに合わせて車種を選んで、購入方法を選択すればいいですよ。
なぜ、購入方法を選ぶことになるの?


今後10年以上は、自動車社会の変化や技術の進歩がどうなるのかわからないので、従来のような一括購入で所有すること以外の選択肢を考慮しておいたほうがいいですよ。
どんな購入方法があるの?


従来からある分割払いに加えて、10年前からある支払い期間後の下取り価格を予め決めて差し引いた金額だけを分割払いする「残クレ」がありますよね。
そして、最近注目されているのが、「個人向けカーリース」で「残クレ」に似ていて、さらに購入時の支払い期間中の諸費用や税金、保険料、法定点検などが含まれていて、毎月定額を支払い続けて、個人の使い方による燃料費や駐車場費、有料道路通行費、洗車費用などだけを負担する購入方法があります。
3年間もしくは5年間しか乗らないのであれば、その期間分の負担で単純に利用できる事がポイントです。
そうだね
ガソリンスタンドが、ガソリンから電気を供給するような社会構造の変化が落ち着くまでのクルマ選びなんて、答えがでなさそうだから、利用期間を割り切ったほうが考えやすいね。


そうですね。
それらの選択肢を理解した上で、つよしさんのライフスタイルあったクルマか、乗ってみたかったクルマを選べばいいのですよ。
今後はクルマを所有する事が減るかもしれませんから。
乗ってみたかったクルマか…
ランボルギーニを所有してみたかったな!
時代に逆行して、レーシングカーのレプリカを乗ってみたい。
そして、あの上に開閉するドアからさっそうと登場したいな。


それはそれでいいですけど…
冗談だよ!
安全第一!
先進機能満載のクルマにするよ。
あとは、購入方法を決めるだけだね。


そうですね。
先進機能満載のクルマなら、これから数年間の変化する自動車社会に対応できそうですね。
いいと思いますよ。
ノッティーさんと話したおかげで、考えが整理できたよ。
ありがとう、帰って妻と相談するよ。


つよしさんは、購入方法の選択肢の情報と会話する事で、考えが整理できたようです。
つよしさんのように、クルマの相談が急増しています。
現状の情報を下記にまとめましたので、ご一読いただき今後の参考にしていただければ幸いです。
ガソリンやディーゼル軽油、LPガスなどの化石燃料を内燃機関(エンジン)で駆動させて、大気汚染要因の排気ガスや温室効果ガスの要因となるメタンや二酸化炭素などを排出する自動車の規制が全世界で既に予定されています。
日本国内においても、2030年代中には内燃機関でのみ走行する自動車は新車販売できなくなります。
エンジン駆動の自動車規制の背景
日本における二酸化炭素の排出量の自動車の走行よるものの割合は約18%を占めています。
二酸化炭素などの温室効果ガスにより、地球規模で気候変動が発生して、温暖化を抑えることが直近の課題です。
それには、限りがある化石資源に依存しない、再生可能エネルギーを中心とした持続可能な脱炭素社会を構築しなければなりません。
この問題は世代を超えた時間で考えなければなりません。
自分の生きている間には影響がないと他人事では済まされません。何も落ち度がない、若い世代や今後生まれる命などに課題を悪化させて押し付けることになるのです。
したがって、地球上の全世代が持続可能な取り組みを理解して、積極的に取り組まなければなりません。
日本の自動車社会の脱炭素化への取り組み
日本はエンジン技術が優れており、燃費が良くトラブルが少なく品質がよいため世界中で支持されています。
さらに低燃費を実現するために、エンジン技術を応用した、電気モーターと組み合わせてタイヤを駆動させる異なる動力のハイブリッド技術で、トヨタやホンダが世界をリードしています。
また、量産型の電気自動車では、日産自動車のリーフが2010年から50万台を全世界で販売しており、充電や技術の蓄積があります。
日産自動車は他社のハイブリッド技術とは異なり、電気モーターのみで走行し、その電力を発生させるための発電用エンジンを搭載して、充電することなくガゾリン給油にて走行距離を伸ばす電気自動車(レンジ・エクステンダー)が、環境負荷や燃費性能を意識する消費者に好評で販売台数が登録車種で常に上位をキープしています。
日本は蓄電池技術は海外に比べて劣りますが、モーターはエンジンと同じくノウハウがあります。
多様化する駆動方式の概要
| 名称 | エンジンの役割 | モーターの役割 | 走行の主体 | 走行用蓄電池の容量 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン車 | 走行 | 搭載なし | エンジン | 搭載なし |
| マイクロハイブリッド車 (アイドルストップ車、充電制御車) | 走行 | 回生ブレーキによる発電 | エンジン | 搭載なし ※電気二重層コンデンサにて充放電 |
| マイルドハイブリッド車 | 走行と発電兼用 | エンジン走行時にモーターがアシスト 回生ブレーキによる発電 | エンジンのみの走行または、 エンジン走行時にモーターがアシスト | 小容量 |
| ストロングハイブリッド車 | 走行と発電兼用 | モーターのみで走行または、 エンジン走行時にモーターがアシスト 回生ブレーキによる発電 | モーターのみの走行または、 エンジン走行時にモーターがアシスト | 中容量 |
| シリーズハイブリッド車 | 発電専用で効率優先の定速回転 | モーターのみで走行 回生ブレーキによる発電 | モーター | 中容量 |
| プラグインハイブリッド車 | 走行と発電兼用 | モーターのみで走行または、 エンジン走行時にモーターがアシスト 回生ブレーキによる発電 | モーターのみの走行または、 エンジン走行時にモーターがアシスト | 比較的大容量で外部充電可能 |
| 電気自動車 | 搭載なし | モーターのみで走行 回生ブレーキによる発電 | モーター | 特大容量で外部充電専用 |
自動車の自動運転化
一方で、自動車とITC技術を融合した、自動化技術は今や国際競争となり、競争により技術の進歩が加速しています。
自動運転車の定義および名称
| レベル | 概要 | 運転の主体 | 対応する車両の名称 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | システムが前後(アクセル・ブレーキ操作)・左右(ハンドル操作)のいずれかの車両制御を実施 | 運転者 | 運転支援 |
| レベル2 | システムが前後(アクセル・ブレーキ操作)・左右(ハンドル操作)の両方の車両制御を実施 | 運転者 | 高度な運転支援 |
| レベル3 | 特定条件下においてシステムが運転を実施 (当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システム の介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要) | 自動運行装置 (自動運行装置の作動が困難な場合は運転者) | 特定条件下における自動運転 |
| レベル4 | 特定条件下においてシステムが運転を実施 (作動継続が困難な場合もシステムが対応) | 自動運行装置 (自動運行装置の作動が困難な場合は運転者) | 特定条件下における完全自動運転 |
| レベル5 | 常にシステムが運転を実施 | 自動運行装置 | 完全自動運転 |
通信技術を利用して、その時の最適な道案内をすることで、渋滞を回避して無駄な燃料消費を抑える事に役立っています。
日本国内では自動運転レベル2(自動運転ではなく運転支援とも表現する)の機能が搭載された、速度制御や衝突軽減機能の前後移動の走行運転支援、車線逸脱制御の左右移動の操舵運転支援が一般的になりつつあります。
走行制御か操舵制御のどちらかの場合は自動運転レベル1(自動運転ではなく運転支援とも表現する)あとなります。
また一部で自動運転レベル3(高速道路走行などに限定した自動運転)が市販化されています。
国内の地域を限定して、自動運転レベル4(ドライバーが緊急時に対応するする条件付き自動運転)の社会実験が実施されています。
また自動車会社や電機メーカー、新興メーカーが自動運転の技術を競走しており、進歩の加速の要素になっています。
今後は自動運転レベル5(条件なし・ドライバー不要)な自動車が社会全体で共有して必要に応じて呼び出すなどの利用方法になり、現在のマイカーのように個人などで所有することは減少すると考えられています。
EUでは速度自動抑制が義務化、日本も導入検討へ
電気自動車と自動運転と通信ネットワークを組み合わせ、道路標識を認識して自動で安全な速度に制御する取り組みがあります。
EUでは、2022年以降に発売される新車は速度自動抑制「ISA(インテリジェント・スピード・アシスタンス)」の搭載が義務化されます。また、既存車に対しても2024年5月までに装置の搭載を義務化する事が決まっています。
従来のような一般的ではない最高速度や最高出力などの過剰な高速域までの性能は必要ではなく、また病院や学校の近くでは自動的に速度を抑制して、歩行者との事故を抑制するためです。
高性能で高出力な自動車で競う時代は終わり、社会の中で様々なものに配慮しながら安全に移動する手段として期待されています。
最適な購入時期はいつ?
前述のエネルギー問題と自動運転化の2つの要素と、社会構造が変化していく現在は、国内の消費者が自動車の購入や買替えの適切なタイミングがわからなくて、安全運転支援機能が備わっていない自動車を車検を受けて乗り続けている方が多いと思います。
現在の国内での自動車の購入時や維持費には、さまざまな費用が必要であり、環境性能に応じて減税や購入時の補助金の対象になっています。ですが自動車の高機能化により販売価格が10年前の自動車より割高になり、消費者の負担額は大きくなっています。
高機能な安全運転支援機能が搭載されている車種は、事故発生率が相対的に少ないため任意保険料が乗り換え以前の想定より安くなる場合があります。
自動車の購入方法
一括購入
現金で一括購入して、車検証の所有者と使用者が同じになります。支払い済みで残債などがないため、いつでも売却することが可能です。
分割払い購入(ローン)
自動車販売会社などが実施している36ヶ月や60ヶ月などの期間を決めて分割払いで、利息と手数料が上乗せされ、支払いが完了するまでは、車検証の所有者は信販会社になります。
支払いが完了すれば車検証の所有者名義を書き換えることが可能で、その後に必要に応じて売却が可能です。
残価設定型分割払い(残クレ)
自動車販売会社などが実施していて、購入契約前に分割払い完了後の下取り価格を差し引いた金額を36ヶ月や60ヶ月などの期間を決めて分割払いします。
分割払い完了後の時点での下取り価格が社会情勢などで下がる可能性があっても、契約時に決めた下取り価格は差し引かれているため、時代の変化のリスクは軽減できます。
下取り条件は走行距離などが決められており、超過した場合は別途負担が必要になります。
また、残価設定分を全て支払うことで車検証の名義変更が可能になり、継続して使用することができます。
個人向けカーリース(マイカーリース)
自動車販売会社が提供している自動車を取り巻く環境が変わる過渡期に注目されています。
購入時の費用と36ヶ月や60ヶ月などの決められた期間に通常発生する諸税や保険料、車検などのら法定点検費用を全てを毎月の定額費用を負担することで利用可能なプランです。
残価設定型クレジットと同様に、決められた期間が経過すれば下取りされることを前提にしているため、下取り価格は予め差し引かれています。
ガゾリンなどの燃料費用や有料道路費用、駐車場費用、洗車費用などが発生する程度です。
購入方法の概要
| 購入方法 | 利用期間 | 車両本体価格の支払額 | 諸費用 | 税金 | 任意保険料 | 法定点検費用 | 使用条件 | 支払い中の扱い | 支払い期間満了後の扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括購入 | 条件なし | 全額 | 別途 | 別途 | 別途契約 | 別途 | なし | 所有者 使用者 | 購入時から所有者 |
| 分割購入 | 条件なし | 全額 | 別途 | 別途 | 別途契約 | 別途 | なし | 使用者 | 所有者となる |
| 残価設定型分割購入 | 支払い期間 | 支払い期間後の下取り価格を予め差し引いた金額 | 別途 | 別途 | 別途契約 | 別途 | 走行距離などの条件有り | 使用者 | 返却または、 下取り設定価格を支払って買取(所有者となる) |
| 個人向けカーリース | 支払い期間 | 支払い期間後の下取り価格を予め差し引いた金額 | 利用期間の分割払いに含まれる | 利用期間の分割払いに含まれる | 利用期間の分割払いに含まれる | 利用期間の分割払いに含まれる | 走行距離などの条件有り | 使用者 | 返却または、 下取り設定価格を支払って買取(所有者となる) |
購入時期が悩ましいけど何もしなければ…
技術の進歩が激しくて、購入のタイミングが悩ましいところですが、買い替えを先延ばしすると所有年数によって、車検費用や課税額が増額されます。
何もしなければ、安全性に劣った自動車として保険料が下がりにくい場合もあり、先延ばしすることさえも不利益になるのが現状です。その場合は現在所有している自動車を、最後のマイカーとして付き合うことが選択肢になります。
買い替えや購入を検討されているのであれば、「来年になればもっといい自動車が発売される」と先延ばしする口実にするのは以前からよくある話です。
ここ数年間は自動車が毎年大きな進歩をするため、購入の良いタイミングの見極めが難しいため、以前より増してなかなか話が前へ進むことができないこともありますので、情報に敏感になっておく必要があります。
この先は、所有する事が減ることを考慮して、思い切って所有したかった自動車を購入を検討することも良い選択肢かもしれません。
まとめ
自動車メーカーも開発のための技術を結集するために、他の自動車メーカーと連携して、ご存知のように車種のバリエーションを減らしています。
消費者としては、選択肢が少なくなることでさらに購入動機がさらに混乱します。
長期的な展望では、自動車を所有することは今後なくなる事が多くなりますが、今は過渡期で世界中の自動車の利用者が悩んでいます。
個人のライフスタイルや、人生のライフステージに応じてマイカーを変えることが望ましいく、さらに社会情勢を加えて考慮して、必要であれば購入を検討し、自分に合った購入方法で検討することが、現状の選択肢といえます。
最適解が何かは結論が出ませんが、現状の情報を集約してますので、選択肢を検討する参考になれば幸いです。
- 作成:令和3年2月23日
- 文:能登健
- 出典元:国土交通省、環境省、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業
- 画像:ぱくたそ、いらすとや