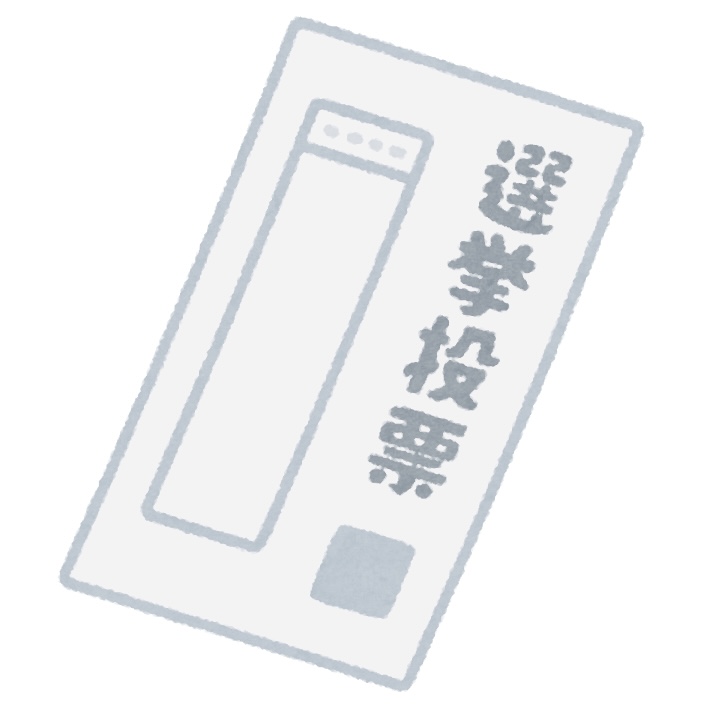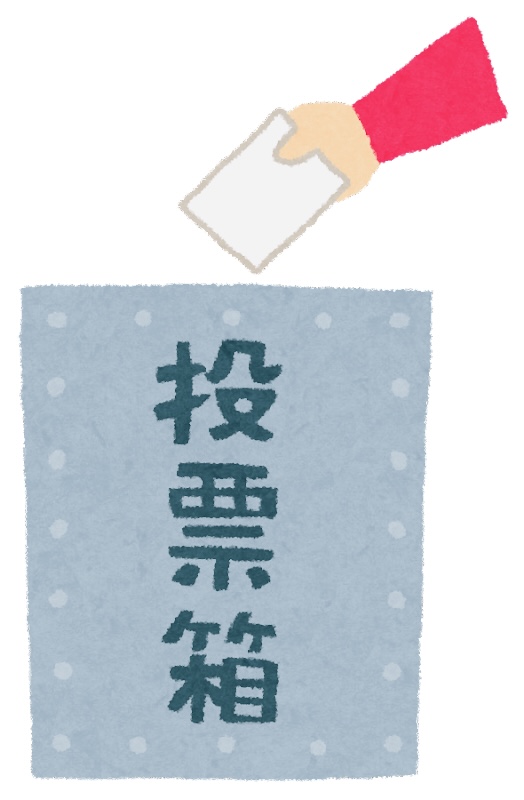【投票はあなたの声】責任ある大人のたしなみ、投票する「カッコいい大人」
投票に関心がない方へ
「投票はあなたの声だ」 「私も投票します」
橋本環奈さん、二階堂ふみさん、菅田将暉さん、コムアイーーさん、ローラさんなど、14人の俳優やミュージシャンらが選挙を語る動画が公開されました。
つくったのは、自主制作プロジェクト「VOICE PROJECT 投票はあなたの声」。
※政府、政党、企業などの関わりのない市民による自主的なプロジェクトです。
10月31日に投票日を迎える衆議院議員選挙に向けて、一票の大切さを動画で伝えています。
多くの国民が、事実から目を背け、聞いていないと耳を塞ぎ、無関係を装い投票行動を起こさなければ、時代の変化から日本全体が取り残されます。国民全体の不利益に間違いなく連鎖します。
30年間の賃金の上昇がないことや、資源のない日本で加工による付加価値の技術産業が空洞化したことで、現役世代の方は痛感していると思います。
今後は、国民一人ひとりの投票行動でどのように変化するか、将来世代に対して持続可能な重たい責任があります。
選挙に投票へ行かないで、自分を失敗を周囲の環境などに責任転嫁する事は「カッコ悪い」、「ダサい」、「ウザい愚痴」と思われます。
それは、大人として責任転嫁は愚の骨頂と軽蔑されますし、さらに投票に参加することなく、愚痴を言う方は、政治に関してトンチンカンな事をさらけ出す傾向にあります。
大人の有権者として、近い将来のために投票する「カッコいい大人」でいるようにしましょう。
今回の衆議院議員選挙
第49回衆院選は令和3年10月19日に公示され、31日投開票に向けて12日間の選挙戦に入りました。
18歳以上の方が有権者(選挙の投票で候補者を選ぶ権利を持つ者、すなわち選挙権を有する者)となり、投票が可能です。
各党はコロナ対策の給付金をチラつかせて、人気を取ろうとしていますが、筆者には単純に形式を変えた有権者に対する買収行為しか見えません。
公職選挙法違反で、直前に裁判で判決が確定した国会議員がいたばかりですが、懲りないのでしょうか?
与党も野党も説明責任を求める立場にはないように思えます。
政治家としての品位がなく、国費(将来へのツケ)から支出する責任も兼ね備えて欲しいものです。
衆議院議員選挙について
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙権の条件(衆議院議員選挙と参議院議員選挙の場合)
- 日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
それでは、海外の選挙権年齢はどのようになっているの?
現在海外では「18歳以上」が主流です。国立国会図書館の調査(平成26年)では世界の191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。
例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳以上となっております。
選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
今回の衆議院議員選挙の問題
一票の格差問題
今回の衆議院議員選挙の全国289小選挙区の「1票の格差」は最大2.09倍となっています。
有権者数は1億562万2860人。今回の衆議院議員選挙では、小選挙区で最多は東京13区(足立区の一部)の48万2445人で、最少は鳥取1区(鳥取市など)の23万1313人となっています。
都心部と地方で開きががあり、国政に反映させる投票の権利を地方の有権者は、都心部の有権者に対して2倍あります。
憲法14条ではすべての国民は「法の下に平等」だと定めており、矛盾が生じています。今回は最高裁が問題視する格差2倍を超えています。
つまり、1人の衆議院議員を選ぶ小選挙区では、東京13区の48万2445人と、鳥取1区の23万人1313人では、単純に鳥取1区の1票の重みづけが東京13区の2倍になります。
すなわち、都市部では1票の重みづけが低くなり、地方では1票の重みづけが高くなり、地方から選出される衆議院議員が多くなり、地方の選出された地元の意見や政策が比較的多く反映されることになります。
結果的に地方の有権者の1票の影響力が都市部より2倍強くなっています。
世代間投票率の問題
平成29年の第48回衆院選では、50歳代以上の投票率が、40歳代以下と比較して高くなっています。
| 有権者の年代 | 投票率 |
|---|---|
| 10歳代 | 40.49% |
| 20歳代 | 33.85% |
| 30歳代 | 44.75% |
| 40歳代 | 53.52% |
| 50歳代 | 63.32% |
| 60歳代 | 72.04% |
| 70歳以上 | 60.94% |
| 全体 | 53.68% |
世代間人口格差の問題
現状では労働人口2人が高齢者1人の社会保障を支えている状態といえます。
そのため、現役世代の可処分所得(社会保障費などを差し引いた所得)が減少しており、労働時間の長時間化と複雑化で、自らの生活のゆとり(時間的余裕、精神的余裕)がなく、自らのことでさえ考える事を先延ばしせざるを得ない状態になっています。
これは社会構造的な問題で、今の高齢者が現役世代の時から予見できていた事を先送りしたためです。
不幸にも、その高齢者を精神的・時間的・経済的余裕がない現役世代が、社会保障や介護などの実質的な負担をしている状態にあります。
政治家がターゲットしている世代が、団塊の世代以上の有権者に向いているので、他の世代は理不尽な負担を強いられています。
| 年齢 | 人口(数) |
|---|---|
| 15歳未満 (新生児から義務教育中の青少年の人口) | 1490万5千人 |
| 15~64歳 (義務教育を終えた労働人口) | 7421万4千人 |
| 65歳以上 (高齢者人口) | 3629万8千人 |
| 総人口 | 1億2541万7千人 |
選挙の諸問題の総括
実質的に社会保障の多くを負担している現役世代に対して、65歳以上の人口と有権者の投票率の高さが、反映されて高齢者対策に優先度が高くなり、少子化対策が数十年間進んでいません。したがって、30歳代以下の方はキャリアプランや人生設計を立てられないまま、学生から社会人になり、政治に翻弄されている状態になっていることが多いのが現状です。
また、労働賃金が人口割合の多い高齢者を支えるための社会保障費などの上昇で、可処分所得(実質的な所得)の減少が続いています。
お世辞に言っても持続可能な社会が構築されているとは言い難く、現役世代の不安は増大する一方です。
政策の方向性を変えるには国民の理解など時間がかかる
現役世代の投票率が高くなったとしても、人口割合の構造的な事実から、高齢者世代の投票者数を上回る事は困難です。
その弊害として、人口が少なくかつ投票率の低い世代は、政治家から軽視され、政策の優先度が下がります。
国際的に見て政治家の高齢化率が高く、多様性のある政治が著しく遅れている
前述を逆手に取れば、将来を担う世代の投票率が上昇すれば、政治家は軽視できなくなり、本格的な社会構造の根本的な改革が始まるかもしれません。
被選挙権は海外より年齢が高く、幅広い世代の政治参加ができないのが日本の現状です。これらも若い世代の政治への関心が高くなり、投票率が上昇して政治への影響力が大きくなれば、選挙権の年齢引き下げのように、被選挙権の年齢引き下げもあるかも知れません。
現在の多くの政治家の既得権益を自己保持
これらの選挙システムに関する諸問題は、現状の多くの政治家が、既得権益を自己保持するために、国民の利益より、自己の立場を優先しているための弊害です。
政治家は当選することが仕事になっている
政治家は自分自身が当選しなければ無職になります。つまり政治家の身分に執着しているのです。選挙で当選して政治家の身分に就くことが大きな目的になっていて、政策より選挙対策が活動の大きな割合を占めています。
政治家は選挙活動で疲弊して、国会という多数決の議会で、委員会では高度な専門知識を有する官僚と議論を尽くすことになります。
政治家は手柄が欲しいが、国民の利益になるアイデアが枯渇している
政治家は議会で手柄をあげて、次期選挙の活動のネタに繋げたいのは山々ですが、どうしても現場の人は選挙で選ばれた議員といえど、担当している委員会に対しても思考が硬直して、アイデアが枯渇しています。
アイデアをそっと伝えることができれば、意外と活用している場合が多いです。
筆者も何度もアイデアを法律に沿った手段で、そっと伝えた事は何度かあり、アイデアがほぼ活用されることもありました。
こうなると政治家になる意味があるの?…と疑問は出ますが、それは別にして、みなさんの等身大のできる投票行動にて、有権者としての責任を、将来の世代に対して果たしましょう。
- 作成:令和3年10月20日
- 文:能登 健
- 出典元:VOICE PROJECT 投票はあなたの声、総務省
- 画像:いらすとや